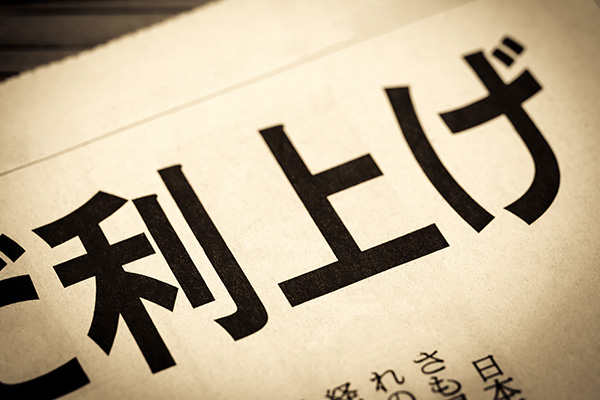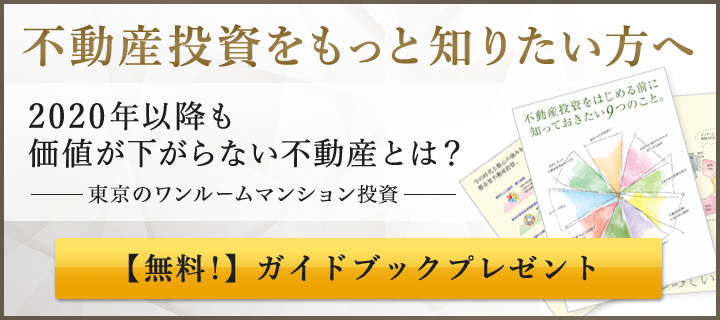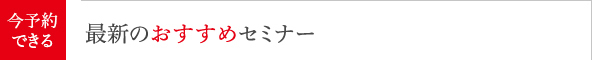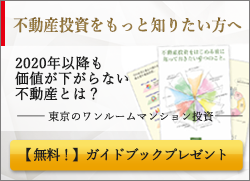25年の1月24日に、日銀は政策金利(誘導目標金利)を0.25%から0.5%へ引き上げることを決めました。これで、昨年3月、7月に続いて過去1年間に3回の政策金利の利上げが行われたことになります。
政策金利の上昇は、金融全般に影響がありますが、とくにダイレクトに反応するのは短期プライムレート、そして借入時の変動金利です。不動産投資において多くの方が変動型金利での借り入れを行いますので、気になるところです。
政策金利上昇の背景
1月24日の政策金利の上昇は、「大方の事前の予想通り」ということで、前後の株式市場は大きな動きはありませんでした。物価上昇をみれば24年後半のコアCPIは+2.5%~2.7%で推移しており、また賃金の上昇も見られることから0.25%分の利上げ(誘導目標金利0.5%)に踏み切ったようです。
政策金利の上昇により、多くの金融機関では3月分からの短期プライムレートの上昇が発表されました。
変動金利のベースとなる短期プライムレートとは
不動産投資融資、あるいは住宅ローンの変動型の金利は、短期プライムレートがベースとなっています。
「短期プライムレート」とは、銀行などの金融機関が信用力の高い優良企業向けに1年未満の短期貸出融資の際に適用する最優遇金利のことです。(ちなみに、1年以上の場合は、長期プライムレートが適用されます)。
政策金利の上昇に伴い、短期プライムレートを上げる金融機関が多いようです。
24年7月末に政策金利が3月0%→7月0.25%となった際には、3月の時点での政策金利の誘導目標が0~0.1%と幅を持たせていたこともあって、それまでの1.475%から1.625%と、上昇は小幅に留まり0.15%分を引き上げる銀行が多かったようです。
しかし、今回は政策金利の上昇分である0.25%引き上げる銀行が多いようです。現在(25年1月末)の短期プライムレートは、1.625%の銀行が多く、これが3月からは0.25%分上昇し1.825%となりそうです。
不動産投資ローンでの変動金利は、概ねこの短期プライムレート付近の金利ですが、住宅ローンの変動金利は、短期プライムレートからさらに優遇金利分を引いた金利が適用され、現在の短期プライムレートよりも約1%程度は低い状況です。前述のように、短期プライムレートは「最優遇」金利ですので、それ以上に「優遇された」金利が適用されるのが住宅ローンということになります。
さて、こうなると変動金利で住宅ローンや不動産投資のための融資を受けている方は心配になります。
変動金利は上がるのか?
ご承知のとおり、借入時の金利には、「変動金利」と「固定金利」があり、現在は住宅ローン融資において約7割の方が、不動産投資でも多く方が「変動型」を選択しているようです。
前述のとおり前回(24年7月末)の政策金利の利上げが行われた際には、その後の短期プライムレートは0.15%上昇しました。そして主要銀行において変動金利で借りている既契約分に関しては0.15%の引き上げが行われました。
今回もおそらく4月以降分から0.25%引き上げが行われる可能性が高いものと思われます。
ただし、前回の時は新規契約分に関しての利上げを行う銀行もあればそうでない銀行もあり、対応が分かれました。
今回は、前回と異なり新規契約分も上げる銀行が多いと思いますが、融資契約を獲得したい銀行では据え置きの可能性もあります。
変動金利上昇の影響は限定的
変動金利が上昇すれば当然利息分が増えますが、現在は2.5%程度のインフレ状況が続いており(そのため金利が上がっている)、インフレ状況下では家賃の上昇も見られます。そのため、キャッシュフローでみればプラスとマイナスで、それほどの影響はないものと思われます(家賃の上昇タイミングの時差はあります)。
また、確かに政策金利はこの1年で0.5%上昇しましたが、インフレ率(約2.5%)と自然利子率(ほぼ0%)を換算すれば、インフレ率がほぼ0%だった21年ごろと比較すれば、「実質的には低い」という状況です。
今後、政策金利が0.75%~1%程度になる可能性もあると思いますが、そのような状況になるとすれば、インフレ率がいまのような2%を超える水準が続いているときということになりますので、この程度までの上昇ならば、不動産投資市況に大きな影響はないと思われます。